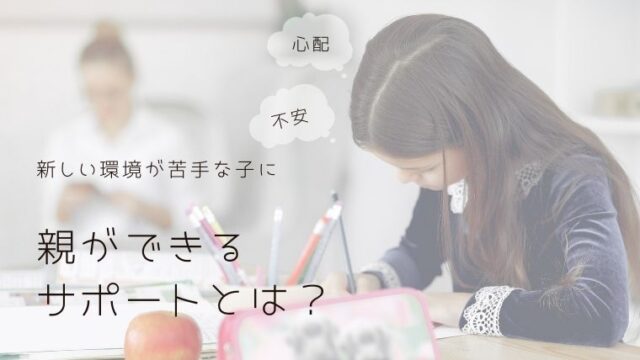学校の先生に相談できる?高校生の思いと先生の対応から学んだ大切なこと

お子さんが学校や友達のことで困っているとき
「これって先生に相談してもいいのかな…」と迷うこと、ありませんか?
小学生なら連絡帳に書くこともできますが、高校生にもなると学校と関わる機会はぐっと減ってきますよね。
子どもの自立を考えると、親としてどこまで関わっていいものか、私も迷いながら子育てをしています。
先日、子どもの高校で生徒へのアンケート調査がありました。
学校で困っていることやいじめがないか、早期発見するためのアンケート。
そのときの子どもの思いや先生の対応から、私はとても大きな学びを得たように思います。
今回の私の経験が、少しでも参考になれば幸いです。
アンケートに書くことのハードル
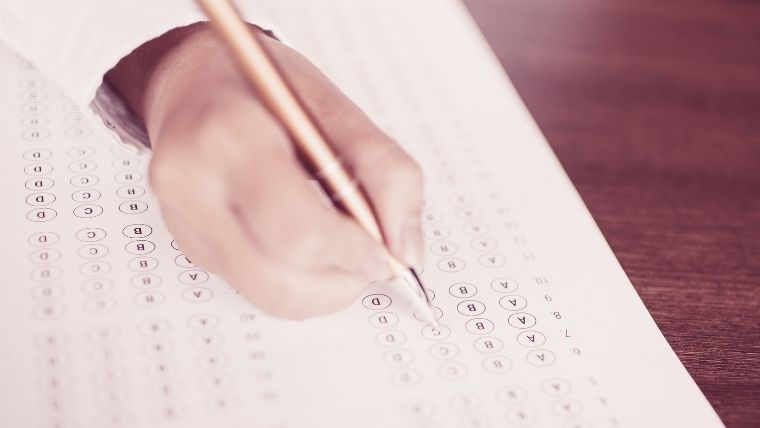
ここ数年、学校では子どもや保護者へのアンケート調査が行われるようになりました。
高校生くらいになると、大人と話をしなくなる子も増えてきます。
ひとりで悩みを抱えて困っている子を把握しサポートしていくために、とてもいい取り組みだと私は思っています。
ところが、子ども側からするとそうでもないらしいということを知りました。
書いたあとの大人の対応次第では、解決するどころか余計にぎくしゃくしてしまったり、怖くなってしまうこともあるようなのです。
いじめや辛いことがあっても本当のことが書けない、言えないことってありますよね。
夏頃からある先生の言動にたびたび傷ついていた娘は、それを書くか書かないかとても迷っていました。
先生に話を聞いてもらったけど…

子ども同士のことではなく、先生の言動に対して困っていることを伝えるのは、確かに勇気がいります。
親からでも、先生のことを学校に相談するのはなかなか高いハードル。
娘はこのアンケートが行われる前にも、担任の先生や他の先生に相談したことがありました。
でも、

周りの先生も〇〇先生が怖くて言えないみたい。
と、余計にモヤモヤしただけ。
じつは中学生の頃にも同級生とのトラブルで学校に相談したとき、担任の先生は一生懸命対応してくれたのですが、結局解決につながらなかった、ということがありました。
娘はそのことについて未だに納得がいかず、親の私としても「解決できなくて申し訳なかったな」という思いがずっと残っていました。
娘の本音は子どもたちの本音?

「どうせ言っても解決しない」
「勇気を出して話したって、結局先生は動いてくれない」
「それなら最初から言わなきゃよかった」
娘のがっかりしたような声は、今の子どもたちの気持ちを代弁しているように感じました。
何かあったら先生や周りの大人に相談するように、といくら呼びかけても、その時の対応次第では「相談しなきゃよかった」と思ってしまう子もいるのです。
娘の友達の話を聞いていても、相談することを諦めてしまう子たちがたくさんいるんじゃないかと思いました。
私は、今までの学びの場で何人かの学校の先生に出会いました。
本気で子どもをサポートしようと頑張っている先生や、見守っている大人がたくさんいることを知っています。
もし今回、勇気を出してアンケートを提出しても、再び先生や大人の対応に失望したとしたら
娘の中にある「大人に相談したって…」という思いは、より強くなってしまうかもしれません。
それはお互いにとって、よくないことですよね。
先生からの電話

アンケートを提出した数日後、担任の先生が娘の話を聞いてくれました。
でもそれは、やっぱり納得いくものではなく、娘にとっては「まるめ込まれた」感じがしたそうです。
残念に思いつつ、一度先生とお話ししてみることにしました。
担任の先生と電話で話してみると、どうやら娘もうまく伝えられていない様子。
高校生とはいえ、「事実」と「自分の思い」をきちんと伝えるのは難しかったかもしれません。
先生の方も「ちょっと勘違いして受け取っているかな」という気がしたので
娘から伝わっていなそうな部分を補足して「娘としてはこう感じているようです」とお伝えしました。
親も伝え方が難しいですよね。
わが子の言うことだけを100%信じて、こちらの言い分だけをいうわけにはいきません。
相手には相手の感じ方や考え方、受けとめ方があります。
実際、そこが親としては難しいところだと思うのですが、どちらの話も冷静に聞ける客観的な視点が必要だなと思いました。
先生は、娘の話を「もっと簡単に考えていました」と申し訳なさそうに言いながら、しっかりと話を聞いてくれました。
親子で驚いた先生の対応

相談したことで、苦手な先生との関係がより悪化したらどうしようと怖がっていた娘。
その数日後、そのの先生と話をすることができ、「そんなつもりは全くなかった」「申し訳なかった」と、頭を下げて謝ってくれたそうです。
これには私も娘も驚きました。
そんなふうに生徒にきちんと謝れる先生はなかなかいません。
そういう姿を子どもに見せてくれたことは、本当にすばらしいと思いました。
子どもは大人の姿や対応をよく見ています。
娘も「正直、見直した」と言っていました。
今後、先生から多少強い指導があったとしても、娘側の受けとめ方は変わってくるんじゃないかと思います。
感謝の言葉を伝えてみる

その後、たまたま別の件で担任の先生とお話しする機会がありました。
今回のことでは、私はその先生とは一度もお話ししていません。
きっと担任の先生がうまく伝えてくださったんだと思い、

先生が〇〇先生に上手く伝えてくださったんですね。
本当にありがとうございました。
と、感謝の思いを伝えてみました。
そして高校生くらいの子は「どうせ相談したって…」と思ってしまう子もいると思うけれど、
先生がちゃんと対応してくれて解決したことが、娘にとって本当によかったともお伝えしました。
先生は、

人と人なので勘違いすることもあるかと思いまして。
いや、本当に私の方こそありがとうございます!
その瞬間に声がパッと明るくなって、気持ちが上がったのがよく分かりました。
私たち親も、先生といい関係を築いていくことは大事だなと思います。
信頼関係ができると、今までよりも子どもの様子を気にかけてくれるようになる先生が多いです。
結果的に子ども自身が学校で過ごしやすくなると思うと、親と先生との関係はとても大切ですね。
経験から学んだことと大切な伝え方

娘にとっても私にとっても、今回の経験はとてもよかったと思っています。
以前、子育てカウンセラーで心療内科医の明橋大二先生の本を読みました。
子どもが傷ついているときに立ち直るきっかけになるのは、相手からの謝罪であることが多いそうです。
それは子ども同士のトラブルだけではなく、親や先生からでも同じだといいます。
間違ったことをしたと思ったときには、今回の先生のように子どもにちゃんと謝れる親でいたいなと思いました。
そして、先生への伝え方が本当に大事だということ。
子どものことになると、つい感情的になってしまう人もいるかもしれません。
ですが、伝えたいことが伝わらずにクレーム扱いされてしまっては悲しいですよね。
解決にもつながりにくくなります。
普段から先生とコミュニケーションをとりながら、何かあったときは連携できるように、お互いにいい関係を築いていきたいですね。
あなたの何かしらの参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
※現在はライフコーチ・講師・ものづくりカウンセラーとして活動をしています。
よろしければ、こちらも合わせて読んでみてくださいね。