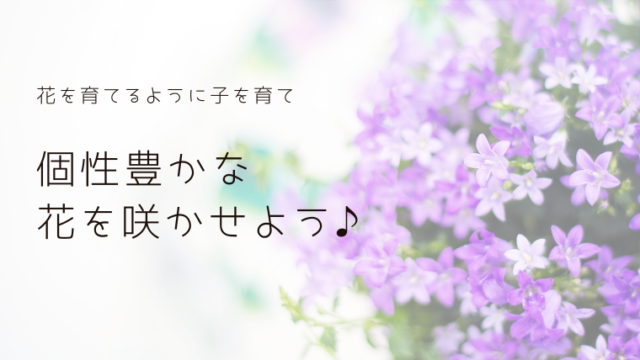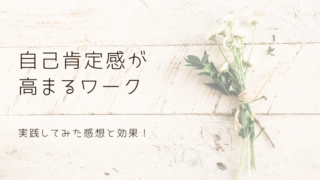心配性のお母さんへ。落ち込んでいる子どもの心を受けとめる接し方のコツ

子どもが学校へ通うようになると、嬉しい反面色々と心配事も出てきますよね。
勉強のこと、お友達のこと、行事のこと。
親であれば子どもへの心配は尽きないかもしれません。
わが家の小学生の息子は、毎日とても元気に学校から帰ってくるのですが、きのうは「ただいまー」の声にいつもより元気がありませんでした。

と聞いても、

と、言いたくなさそう。
どうやら学校で何かあったらしい、ということは分かりますが
- 学校から帰ってきた子どもの元気がない
- なんだかいつもと様子が違う
- 何かあったのか聞いても話してくれない
そんなとき、あなたならどうしますか?
落ち込んでいる子に、どんなふうに声をかけてあげますか?
今回は、「落ち込んでいる子にどう接したらいいの?」と迷っている方に向けて、
私なりに試行錯誤してきて分かってきた心を受けとめる接し方のコツを、お伝えしてみたいと思います。
個人差やお子さんの性格もあると思いますので、あくまでも一例として、対応に迷われている方の参考になれば幸いです。
落ち込んでいる理由を根ほり葉ほり聞き出そうとしない

以前の私は、これがなかなかできませんでした。

先生に怒られたりしたのかな?
と、気になってしまうのです。
私自身が不安を抱えていたり、心配性だったからだと思うのですが、
何年も子どものトラブルに試行錯誤してきて、少しずつどう対応したらいいのかが分かってきました。
子どもが低学年のうちは、わりとその日の出来事を話してくれたりします。
でも、高学年や中学生くらいになってくると「いや、ちょっと」とか「話したくない」と言われることもありますよね。
そんなときは、無理にその理由を聞き出そうとしなくても大丈夫です。
お母さんの頭の中には、次から次へと心配なことが浮かんできてしまうかもしれませんが、
「自分が気になるから」という理由で、根ほり葉ほり聞き出そうとするのは逆効果。
気になるのは、子どものことが心配というよりも、自分が不安だからなんですよね。
私も聞きたい気持ちをぐっとこらえて、余計な声をかけずにそっと子どもの様子を見守るようにしています。
様子を見ながら時々声をかけてみる

見守るといってもどうしたらいいの?と思う方もいらっしゃると思いますが、
私がおすすめなのは、そのことには触れずに普通に声をかけること。

そんなふうに時々声をかけています。

という返事が返ってきたとしても、
「何も聞いてこないけど、お母さんは気にかけてくれている」
ということが子どもに伝わればいいのです。
表情には出さなくても、子どもは嬉しく感じています。
また、夕ご飯にその子の好きなものを作ってあげるのも、「自分を大事に思ってくれている」ことが伝わりやすいのでおすすめです。
子どもによって、わりと甘えてくる子とあまり甘えない子がいると思いますが、
料理をしているときにキッチンにきたり、近くをウロウロしているようなことがあれば、ちょっと甘えたい、構ってほしいというサインかもしれません。
わが家の場合は、そんな感じで近くに座ったりくっついてきたりするので、そんなときは、

と伝えています。
普段そんな会話をしない家庭だと、ちょっと恥ずかしいかもしれません。
けれど嫌がらないようなら、思春期でもぎゅっと抱きしめてあげる。
心細いときや不安なときは、子どもは安心したいんですね。

というと、話し出すこともあれば

ということもあります。もし話したくないというなら、

もし話したくなったらいつでも聴くからね。
と言って、またしばらく様子を見守っています。
話そうとしてきたら忙しくても手を止めて話を聴く

こうやって、「気にかけているけど話したくなるまで待ってるよ」という親の姿勢が伝われば、
子どもは自分のタイミングで話したくなったときに声をかけてきます。
もし話しかけてきたら、そのときは忙しくても手をとめて聞いてあげてくださいね。
- どんな話でも否定しないで聴く
- いい悪いのジャッジをしない
- 相手のことを悪く言わない
これが、話を聴くときのコツです。
たとえば息子の場合、高学年でも体が小さく背が低いことを本人はとても気にしているのですが、
仲がいい友達に「クラスでいちばん背がちっちゃい」とからかわれたそうなんです。
それで落ち込んでいたのです。
大人からすれば大したことがないように思えても、本人にとってはとても悲しい。
自分の努力ではどうすることもできないのだから。
夜になって話しにきてくれたときには、「そっかそっか、そんなことがあったんだね」
「それは嫌だったね」「気にしてること言われたら嫌だよね」と、その悔しくて悲しい気持ちをたくさん聴きました。
子どもが怒りをあらわにして興奮気味に気持ちを吐き出すこともありますが、一通りワーッと話すとスッキリして気持ちを切り替えられる場合もあります。
子どもの方から「話を聴いてくれてありがとう」と言ってきたら、少しだけ優しく励ます。
「ゆっくり成長する子と早く成長する子がいるだけなんだよ」「これからちゃんと大きくなるから大丈夫」と。
- 子どもの話を否定せずに、気持ちを聴く
- 誰が悪いとかいいとかすぐにジャッジしない
- 子どもと一緒になって相手のことを悪く言わない
それを心がけてみてくださいね。
上の子のときにできなかったこと
私は上の子のときに、その聴き方がなかなかできませんでした。
自分の子が何か意地悪されたとか、嫌なことをされたというと相手の子を悪く言ってしまったり・・・。
何があったの?どうしたの?と質問攻めにしてしまったり。
今考えるととても恥ずかしいのですが、子どもが泣いて帰ってきたり落ち込んで帰ってきたときに、どうしたらいいのかが分からなかったんですね。
自分自身が不安で自信がもてないでいたことも大きかったと、今では思います。
子どもの気持ちを受け止めて「話してくれてありがとう」と伝えれば、
「気持ちをわかってくれた!」と感じた子は、また何かあったときには話してみようと思うようになります。
親の方も根気がいりますが、これから子どもが成長して大きな悩みにぶつかったときにも、
- 相談できる相手がいる
- 安心して話せる人がいる
というのは、とても大きな心の支えになるのではないでしょうか。
「この子は必ず乗り越えられる」と子どもの力を信じる
子どもは本来「成長したい」「今よりもっとよくなりたい」という生きる力を持っています。
だからこそ親がその力を信じる。「この子なら必ず乗り越えられる」と信じる。
親が「この子はできる!」と思えばできるし、「この子はできない」と思えばできなくなってしまうのです。
その上で「もし助けてほしいことがあったらいつでも言ってね」と伝えるといいと思います。
子どもは親に話を聴いてもらいながら、気持ちを整理し自分なりに答えを見つけ出します。
落ち込んで「明日学校に行きたくない」と言っていた息子は、話をしたあと少し元気になり「明日学校行く」といいました。
次の日は「〇〇くんがごめんねって言ってくれたから、もういいことにした」と言って帰ってきました。
まだ心に引っかかることがあるのかと思い、

と聞くと、
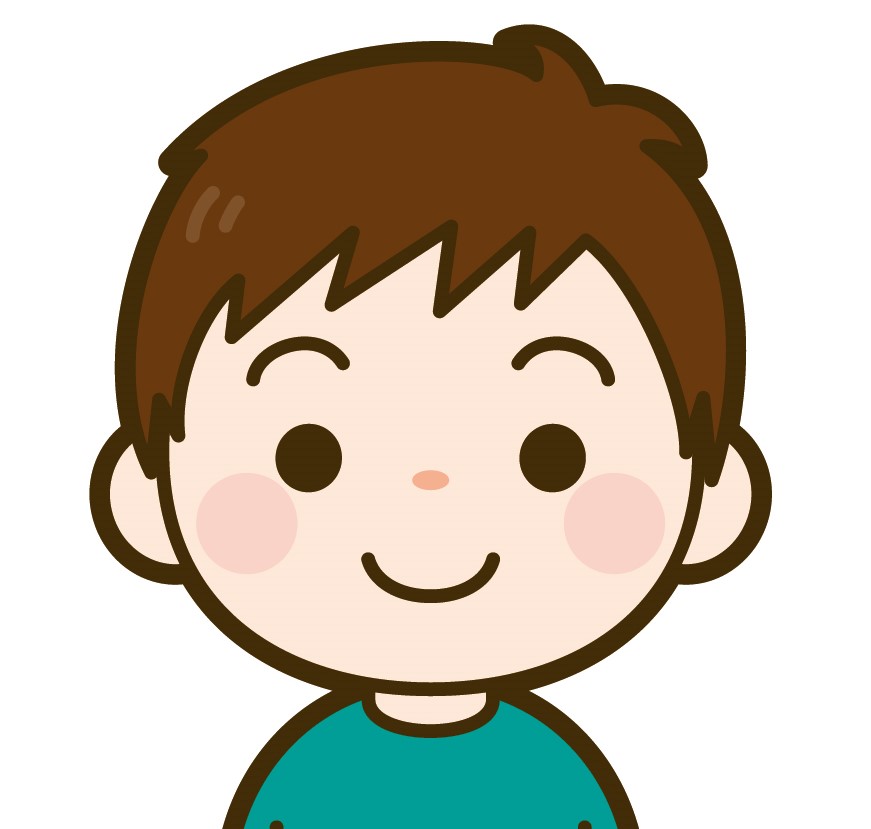
と言って、元気に遊びにいきました。
ちゃんと自分で乗り越えたのです。
ちょっとした子ども同士のいざこざなら、あくまでも子どもの問題として捉え、親が代わりに悩まないこと。
これが、大切なんですね。
子どもが成長するための課題だと捉えて、大きな気持ちで見守ってあげてくださいね。
まとめ:落ち込んでいる子どもの心を受けとめる接し方のコツ
私が試行錯誤してきた経験からお伝えできることを、お話ししてみました。
このような接し方をしていくことで、子どもの中に安心感が育っていきます。
今回の例は、友達とのちょっとしたいざこざでしたが、上の子のときはいじめや仲間外れなど悩むことがたくさんありました。
特に女の子は難しいなと感じます。
また、子どもの個性も様々です。
家庭だけで解決できないときは、学校や先生、その他の場所で相談してみることも選択肢のひとつ。
私もスクールカウンセラーの先生には、随分とお世話になりました。
今もときどきお会いしていますが、私自身が安定して子どもに向き合えるようになったのも、先生の存在が大きかったと思っています。
ただ相性もありますし、相談したからと言ってすぐに解決する問題ばかりではありません。
必要なのは、安心できる家庭や居場所、信じて見守ってくれる環境が大切だと思うのです。
そして、親にできることはあくまでもサポート。
安心できるあたたかい環境があってこそ、外で辛いことがあっても乗り越えられる。
その環境をつくるためにも、お母さんたちには自分のことを大切にして、笑顔で過ごしてほしいなと思っています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
現在はライフコーチ・講師・カウンセラーとして活動をしています。
よろしければ、こちらも合わせて読んでみてくださいね。