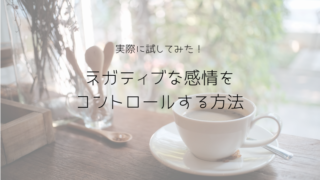新しい環境が苦手で不安や心配が強い子に、親ができるサポートとは?
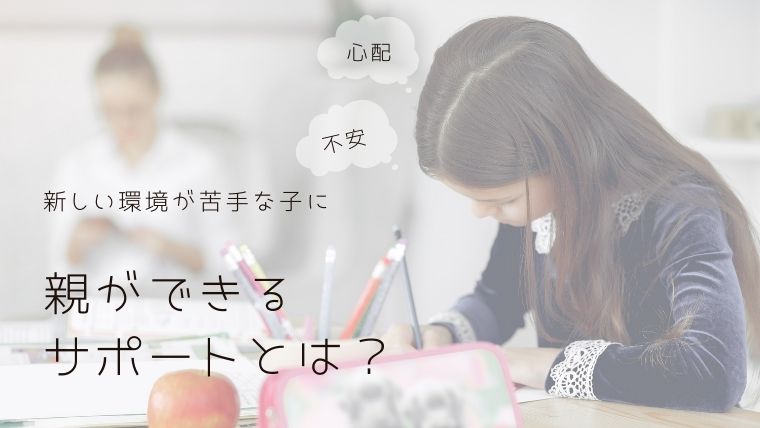
この春、進級や進学で環境が変わった人も多いのではないでしょうか?
お子さんの様子はいかがですか?
4月の終わりから5、6月頃は、慣れない環境で気を張って一生懸命がんばっていた子どもたちにも、だんだんと疲れが出てくる頃ですね。
すんなりと溶け込んでいける子がいる一方で、新しい環境に慣れるのが苦手なお子さんもいると思います。
今回は、環境が変わったばかりでなかなか馴染めなかったり、心配や不安が強いお子さんに親ができるサポートについて、私の経験からお話ししてみたいと思います。
少しでも参考になれば幸いです。
新しい環境が苦手でも大丈夫

環境の変化が苦手なお子さんやお母さんは、引っ越しや進級、進学のたびに親子で苦労しているのではないでしょうか?
私も幾度となく悩み、サポートし、試行錯誤しながらなんとか乗り越えてきました。
新しい環境が苦手といっても様々なタイプのお子さんがいると思いますが、まずはお母さん自身が「大丈夫、なんとかなる!」という気持ちで、子どもと向き合っていきましょう。
小さい頃から新しい環境に慣れるのに時間がかかる
このようなお子さんは人見知りが強かったり、知らない場所や人、まだ経験していないことに対する不安や心配が大きいことがあります。
初めての場所や出会いはワクワクする反面、知らない世界へ踏み出す不安や心配が出てくることもあると思います。
とても慎重で周りをよく観察して、安全な場所かどうか確かめているのかもしれません。
今までも、ゆっくり自分のペースで順応してこれたのなら、多少時間がかかっても少しずつ慣れていきますので、あまり心配しなくても大丈夫だと思います。
お母さん自身がお子さんとは逆で、すぐに馴染んでいけるタイプだったりすると、

と思うかもしれませんが、親子でも顔が違えば性格も違いますよね。
不安な気持ちを聞きながら、お子さんが安心できるような声かけをしてあげてくださいね。
焦らせることなくペースを見守っていきましょう。
感受性が強く色々な刺激に敏感

このようなお子さんは、感受性が強くいろいろな刺激を敏感に察知するところがあります。
誰も気づかないような些細なことにもいち早く気づいたり、先生や教室のピリピリした空気も感じとります。
その他にも、
音や光や匂いに敏感で、それが刺激になって集中できなくなる
大勢のクラスがうるさくて苦手
人が怒られていると自分が怒られているように感じる
とても疲れやすい
などの面があります。
このような傾向があれば、もしかしたらHSC(ハイリー・センシティブ・チャイルド)かもしれません。
HSCは病気ではなく生まれ持った気質のひとつで、とても素敵な部分でもあります。
色々な面で、ひといちばい敏感な気質を持っているのです。
人よりも高感度のアンテナが全身にたくさんついていると考えてみてください。
そのアンテナが自分でも気づかないうちに様々な情報や刺激をキャッチしてしまい、それが疲れやストレスになってしまうことがあります。
また、タフであること、みんなと同じようにできることが求められる学校生活の中では、
人よりも敏感な部分を「弱さ」と捉えられてしまったり、子ども自身も「なんか自分はみんなと違う」と感じて、不安になりやすいかもしれません。
このような気質のために、人より少し慣れるのに時間がかかったり疲れやすいということを、お母さんが理解してあげることが安心に繋がります。
ゆっくり休むことを優先しながら、刺激によって困っていることがあれば、和らげる方法がないかを一緒に考えてあげてくださいね。
小さい頃は平気だったのにだんだん苦手に

中高生くらいになると思春期になり、今までよりも周りの目や反応を気にするようになります。
人と自分を比較して優劣を感じたり、自分がどう見られているかを意識するようになるので、気軽に入っていけなくなってしまう子もいるかもしれません。
その場合は思春期特有のものなので、私はそんなに心配はないと思っています。
心配なのは、
過去にお友達同士で嫌な思いをしたまま解決していない
いじめなどで心が傷ついている
場合です。
このような経験から新しい人間関係を築いていくのが怖いと感じ、人に対して苦手意識をもってしまうことがあります。
その場合は、まず心の傷を癒すことを優先するのがいいと思います。
どのくらい傷つきが大きいかにもよりますが、その子が話をしてくれるのであればしっかりと話を聴き、あなたは大切な存在だよ、ということを伝えてあげてください。
学校にはスクールカウンセラーの先生もいますので、心配なことは遠慮せずに相談してみるのも大切です。
本人やお母さんだけで抱え込んで悩んでしまうと親子で辛くなってしまいますし、相談してみることで色々な気づきが得られることもあると思います。
前向きに解決していけるように、先生や専門家の力を借りながら進んでいきましょう。
子どもをサポートするための大切なポイント

ここからは、色々なタイプのお子さんがいることを理解しつつ、サポートしていくための大切なポイントをまとめました。
- がんばりをそのまま認める
- 子どもの話をしっかり聴く
- 一緒に考える
がんばりをそのまま認める
まずは、子どものがんばりをそのまま認めてあげてください。
子どもなりに毎日慣れない環境の中で、すでにがんばっているのです。
お母さんから見たら、家ではダラダラしていてちっともがんばっているように見えないかもしれません。
それでも「毎日よくがんばってるね」と声をかけてあげてくださいね。
- 朝起きた
- 自分の足で学校に行った
- 授業を受けて部活をして帰ってきた
それだけで、十分がんばっています。当たり前ではありません。
- 朝起きれない
- 学校に行けない
- クラスに入れない
私はそんな娘に様々な経験をさせてもらったおかげで、それが当たり前ではないということを知ることができました。
たとえみんなと同じようにできないことがあっても、今できていることをそのまま「がんばってるね」と認めてもらうことは、子どもにとっては自分の存在をそのまま認めてもらえるということです。
できないことよりも、今できていることに目を向けてみてくださいね。
子どもの話をしっかり聴く

思春期になると自分から話してくることが少なくなるかもしれませんが、子どもが話を聴いて欲しそうなときには、忙しくてもしっかりと話を聴いてあげてほしいと思います。
そして、まずはどんな話も「そうなんだね」と、否定せずに聴いてあげてください。
春から新しい環境に入った息子は、学校に行く前、帰宅後、料理を作っているときにちょこちょこやってきては、

と言いながら、不安そうな顔で側にきます。

そう声をかけると、うんと頷いて
- 新しい学校のシステムがよく分からなくて心配なこと
- 授業時間が長くなりやらなきゃいけないことも多くて疲れること
- クラスに言動がきつい子がいて嫌なこと
- ランチタイムが短くて時間内にお弁当が食べきれないこと
などをポツポツと話してくれました。
そんなときは、

そっかぁ、それは心配だね。
分かる分かる!
ほんとに毎日よくがんばってるね。
そんなふうにお子さんの気持ちを受けとめてあげてください。
心の中のモヤモヤを話すと、大人でもスッキリしますよね。
例えばご主人に心配や不安なことを話したとして、

そんな甘いこと言ってたらやっていけないぞ。
なんて言われたり、怒られたりしたらどうでしょうか?
なんとなく気持ちが満たされないまま余計にモヤモヤしてしまったり、

なんて思って話をするのをあきらめてしまうこともあるかもしれません。
友達と話をしていて共感したりされたりすると、スッキリして少し心が晴れたりしますよね。
話を聞いてもらうだけでも心がホッとして、また前を向く元気が湧いてきます。
お子さんによっては自分の不安な気持ちがうまく言葉にできずに、泣いてしまう場合もあるかと思いますが、
そんなときは「泣いてても分からないよ」ではなく、「うまく言葉にできない」というその気持ちを「そうなんだね」と受け止めてあげればいいと思います。
そうすると、子どもは今感じている思いを少しずつ自分の言葉で話し出すことがあります。
話してくれたら、

話してくれてありがとう。
と伝えると、お子さんはとても安心すると思います。
そして、もし困っていることがあれば、これからどうしたらいいかを一緒に考えることができます。
一緒に考える
”どうしたらいいか一緒に考える”というのは、親が「じゃぁ、こうしなさい」と決めることではありません。
「〇〇は、どうしたい?」「どうなったらいいなぁって思う?」と、お子さんに聞いてみてください。
そして、「何ができそうかな?」「こういう方法もあるね」と、お子さんがどうしたいかを聞きながらできそうなことを話し合ってみます。
でも、決めるのは本人です。
お母さんはお子さんの

こうしたいから手伝ってくれる?
という思いに、

と言ってつきあってあげればいいと思います。
私は息子と相談し、まずはお弁当の量を時間内に食べきれる量に減らしました。
疲れやすいので、家ではゆっくり過ごせるように時間の使い方を見直してみようということになりました。
分からなくて心配なことは先生や友達に聞いてみたり、頼ってみてもいいねと話しました。
色々試してみてそれでも不安だったら、またいつでも話を聴くよ、とも伝えています。
息子は日々のちょっとしたことであれば、大抵話を聴いてあげると笑顔になり、

話したらなんかスッキリしたよ。
と言って元気を取り戻しますが、それでもまた次の日に、落ち込んで帰ってくることはよくあります。
元気になったり落ち込んだりをくり返しながら、少しずついい方向に向かえばいいな、親もそんな気持ちで接してみるといいかもしれません。
心配事や不安、ネガティブなモヤモヤが小さいうちに、その都度話を聴くことでクリアにしてあげる。
話を聴いてもらうことは受け入れてもらうということです。
自分を受け入れてもらって安心できると、また成長に向けて子どもは勝手に前に進んでいきます。
お子さんの様子を見ていて、色々と心配に思うこともあるかもしれませんが、必要なときにはしっかり話を聴いてあげながら一緒に考えていけるといいですね。
まとめ:親ができるサポートとは?

新しい環境になかなか馴染めなかったり心配や不安が強い子に、親ができるサポートと大切なポイントについて、私なりに書いてみました。
すぐに結果を求めずに、長い目でみていくことも大切だと思います。
わが家も現在進行形で、新しい環境になかなか馴染めない子どもの揺れにつきあっているところです。
毎日忙しい中で子どもの話をしっかり聴くというのは、結構大変かもしれません。
けれど、子どもが必要としているときに向き合ってあげる時間は、子どもの心をしっかりと育てている時間だと思うのです。
どんなことにもプラスの面があればマイナス面もあり、マイナスだと思うことの中にもプラスの部分を見つけることができます。
そんな視点で、親の方も気持ちをラクにして、子育てを楽しめたらいいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。

僕はよく優しいって言われるけど、それは家族みんなが優しくて心に余裕があるから優しくできるんだと思う。
だから学校で嫌なこと言ってくる人とかは、「心の余裕がないんだね」って思ってるんだ。
新しい環境に慣れるのに時間がかかったとしても、だからこそ気づけることもあるのですね。